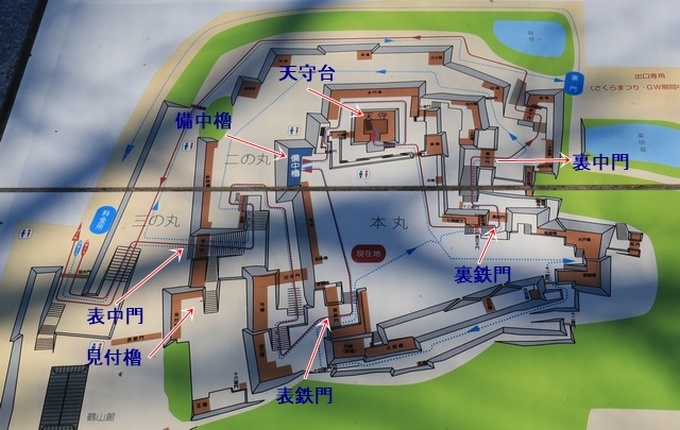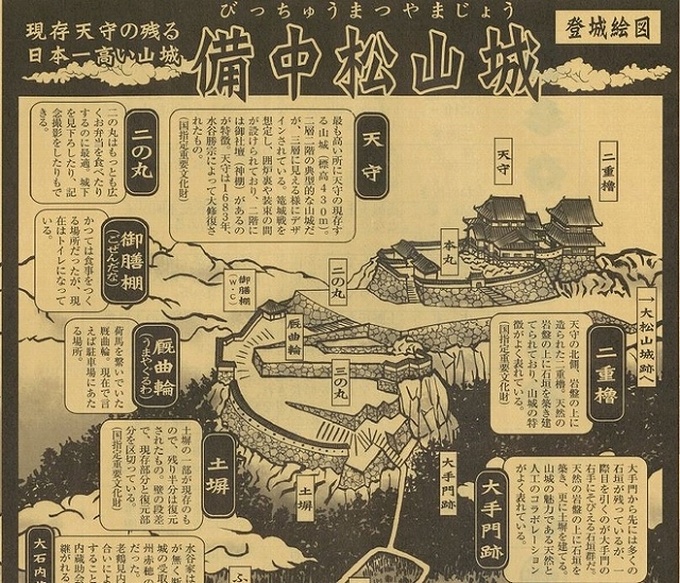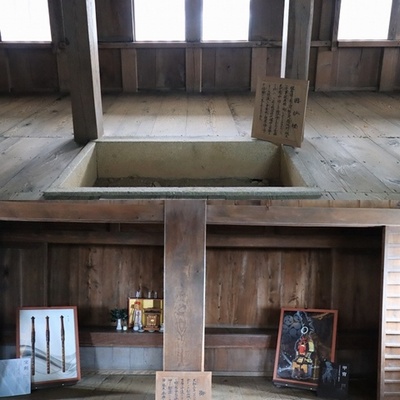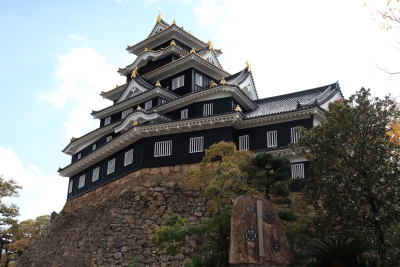33 岡山県
|
日本100名城 |
69. 鬼ノ城 |
||||
|
続日本100名城 |
171. 備中高松城 |
|
■Aランク(日本の100名城) |
||
|
67. 津山城 (岡山県津山市) 国の史跡・三大平山城 津山城は美作国苫田(とまた)郡にあった城で、別名・鶴山城(かくざんじょう)と呼ばれる。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表中門跡。 |
|
|
|
見付櫓に上がる石段。 |
|
|
|
表鉄門跡。 |
|
|
|
備中櫓。 |
|
|
|
備中櫓内部。 |
|
|
|
天守台。 |
|
|
|
天守台から見た備中櫓。 |
|
|
|
津山城が大きかったことがわかります。 |
|
|
|
裏鉄門跡。 |
|
|
|
裏中門に降りる石段。 |
|
|
|
二の丸。 |
|
|
|
68. 備中松山城 (岡山県高梁市) 重要文化財・国の史跡・現存天守・三大山城 松山城は備中国にあった山城で、松山市にある松山城を初め、各地の同名の城との混同を避けるために、一般的には「備中松山城」と呼ぶことが多い。現存天守12城の一つでもあり、この中で唯一の山城である。 (備中松山城HPより転載) https://www.bitchumatsuyamacastle.jp/ (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD) |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
大手門跡。 |
|
|
|
三の平櫓東土塀。(国の重要文化財) |
|
|
|
三の丸。 |
|
|
|
本丸。 |
|
|
|
天守が見えてきました。 |
|
|
|
天守。(国の重要文化財) |
|
|
|
1階には籠城時に城主の食事の準備や暖房に使う囲炉裏、2階には城の守護神を祭る「御社壇(ごしゃだん)」と呼ばれる部屋がありました。 |
|
|
|
二の丸を後曲輪の方へ廻ってみました。 |
|
|
|
紅葉が美しい!。 |
|
|
|
二重櫓。(国の重要文化財) |
|
|
|
69. 鬼ノ城 (岡山県総社市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
70. 岡山城 (岡山県岡山市) 重要文化財・国の史跡・外観復元天守 岡山城は備前国御野(みの)郡にあった平山城で、外観は黒漆塗の下見板が特徴的で、この印象から「烏城(うじょう)」とも呼ばれ、同じ山陽道の隣県の「白鷺城(はくろじょう)」とも呼ばれる姫路城と対比されることもある。 (岡山城HPより転載) https://okayama-castle.jp/ (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
|
|
|
廊下門と渡り廊下。 |
|
|
|
月見櫓。(国の重要文化財) |
|
|
|
城内から見ると三階建。 |
|
|
|
宇喜多秀家による築城時の石垣。 |
|
|
|
中の段。 |
|
|
|
本丸全景。
|
||
|
不明門(あかずのもん)。 |
|
|
|
天守の礎石。 |
|
|
|
天守。 |
|
|
|
天守からの眺め(後楽園側)。 |
|
|
|
天守からの眺め(県庁側)。 |
|
|
|
|
||
|
■Bランク(続日本の100名城) |
||
|
171. 備中高松城 (岡山県岡山市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Cランク |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||