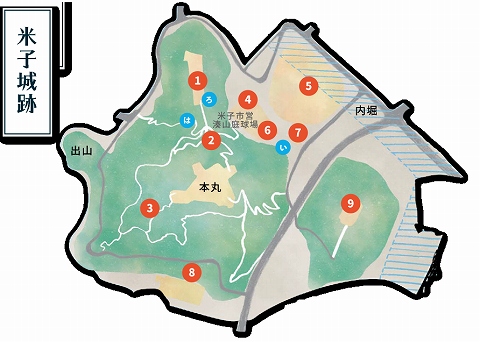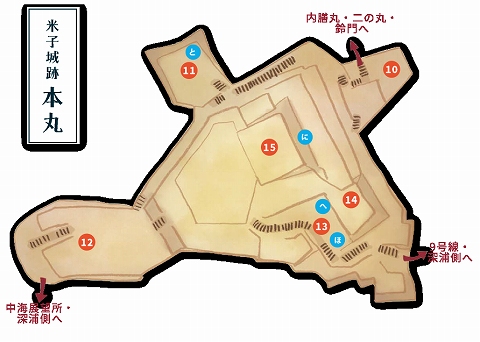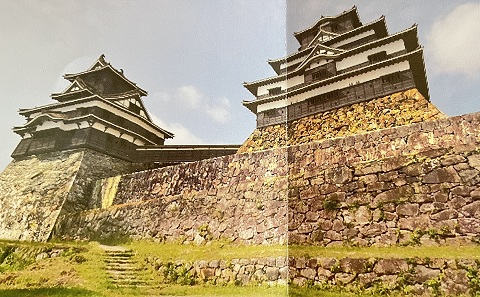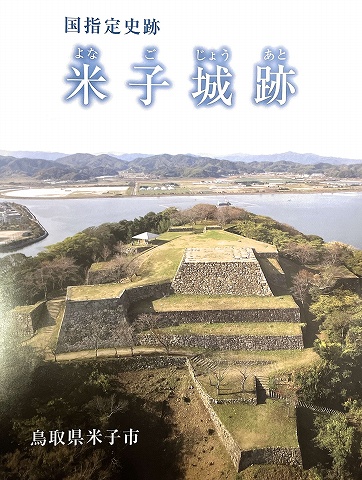31 鳥取県
|
63. 鳥取城 (鳥取県鳥取市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Bランク(続日本の100名城) |
||
|
168. 若桜鬼ヶ城 (鳥取県若桜町) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
169. 米子城 (鳥取県米子市) 国の史跡 米子城は、伯耆国(ほうきのくに)にあった平山城で海城である。 (米子城ホームページより転載) https://yonagocastle.com/ |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
現在の米子城跡図。(マル数字は説明文で使用) 江戸時代に新たに湊山に城が築かれ、山頂の本丸、北側の中腹に二の丸(④)、その下に三の丸(⑤)を置き、戦国期に米子城の主郭であった飯山は出丸(⑨)として利用された、梯郭式の平山城です。 |
|
|
|
現在は駐車場等になっている三の丸から見た二の丸。 |
|
|
|
枡形虎口(⑦)。 |
|
|
|
内膳丸入口。 |
|
|
|
内膳丸(①)。 |
|
|
|
登り石垣(②)。 |
|
|
|
番所跡。 |
|
|
|
本丸(天守台)。 |
|
|
|
左手には2段目、3段目に接続する四重櫓台があります。 |
|
|
|
本丸跡図。 |
|
|
|
天守台(⑮)。 |
|
|
|
天守台の石垣。 |
|
|
|
四重櫓台(⑭)。 |
|
|
|
VRで復元した天守と四重櫓。 |
|
|
|
水手御門(⑫)。 |
|
|
|
本丸から眺める中海。 |
|
パンフレットの写真。
1863年に描かれた米子城絵図 |
|
|
|
||
|
■Cランク |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||