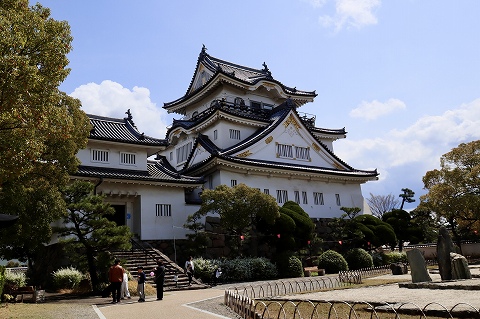27 大阪府
|
日本100名城 |
55. 千早城 |
||||
|
続日本100名城 |
159. 芥川山城 |
160. 飯盛城 |
|
54. 大坂城 (大阪府大阪市) 重要文化財・国の特別史跡・復興天守・三名城 通称「太閤さんのお城」とも呼ばれているが、1959年(昭和34年)の大阪城総合学術調査において、城跡に現存する櫓や石垣などは徳川氏、徳川幕府によるものであることがわかっている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E5%9F%8E |
||
|
取材:大倉(文子による攻城記へ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取材:文子 |
|
|
|
一番櫓(国の重要文化財)と南外堀の高石垣。 |
|
|
|
本丸東側の石垣。 |
|
|
|
空堀。 |
|
|
|
桜門。(国の重要文化財) |
||
|
|
|
|
|
蛸石。
|
「秀頼・淀ら自刃の地」記念碑。
|
|
|
55. 千早城 (大阪府千早赤阪村) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Bランク(続日本の100名城) |
||
|
159. 芥川山城 (大阪府高槻市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
160. 飯盛城 (大阪府大東市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
161. 岸和田城 (大阪府岸和田市) 府の史跡・復興天守 岸和田城は、大阪府岸和田市岸城町にあった平城である。別名千亀利城(ちきりじょう)。江戸時代には岸和田藩の藩庁が置かれた。城跡は大阪府の史跡に指定されている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E |
||
|
取材:杉浦(文子による攻城記へ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取材:文子 |
写真のコメントはWikipedia及びパンフレットを参照しています。 |
|
|
岸和田城マップ。 |
|
|
|
本丸の復興隅櫓と奥には復興天守。 |
|
|
|
横矢掛り(よこやがかり)の石垣。 |
|
|
|
二の丸の積み足された石垣。 |
|
|
|
二の丸の北西のこの石垣の上に、伏見城から移築されたという伏見櫓が建っていたそうです。 |
|
|
|
本丸の復興櫓門。 |
|
|
|
復興天守。 |
|
|
|
八陣の庭。 |
|
|
|
天守から見た八陣の庭。 |
|
|
|
天守入場券。 |
|
|
|
|
||
|
■Cランク |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||