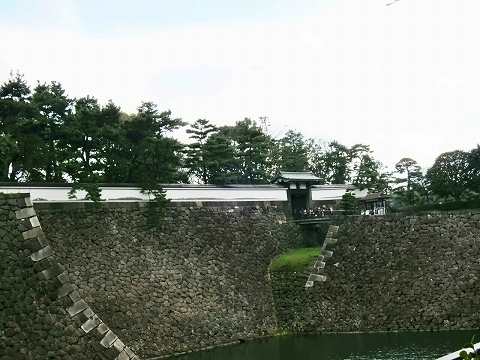13�@�����s
|
���{�P�O�O���� |
|||||
|
�����{�P�O�O���� |
123. ��R�� |
124. �i���� |
|
��A�����N�i���{�̂P�O�O����j |
||
|
21. �]�ˏ� (�����s���c��) �d�v�������E���̓��ʎj�� �]�ˏ�́A�������L���S�]�ˁi���݂̓����s���c����c�j�ɂ�������ł���B�]�ˎ���ɂ����Ă͍]��i�������傤�j�Ƃ����Ăі�����ʓI�������ƌ����A�܂����c��i���悾���傤�j�Ƃ��Ă��B
�]�ˏ�͍�����n�̓��[�ɁA��J�㐙���̉Ɛb���c���z�������R��ł���B�ߐ��ɓ��쎁�ɂ���Ēi�K�I�ɉ��C���ꂽ���ʁA���\���͖�4���ƁA���{�ő�̖ʐς̏�s�ɂȂ����B �@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E |
||
|
��ށF��q�i���q�ɂ��U��L���j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��ށF���q |
�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y���c���O���z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B |
|
|
�c���O���}�b�v�B |
||
|
���c��(�O���c��)�B(���̏d�v������) |
||
|
���c�� �����(��)�ƘE��B
|
���c�� �E��B
|
|
|
�c����B(���̏d�v������) |
|
|
|
����B |
||
|
���� �����(��)�ƘE��B
|
���� �E��B
|
|
|
�j�[��B |
|
|
|
�≺��B |
||
|
|
|
|
|
���싴�ƕ����B |
||
|
|
|
|
|
�s���B |
|
|
|
�����E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |
||
|
|
|
|
|
�c������S��(��d��)�B |
|
|
|
�x�m���E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |
||
|
1657�N�̖���̑�œV�炪����������A�x�m���E�������̓V��Ƃ��Ă��܂����B����ȍ~�A���˂ł͍Č����܂ߓV��̌������T����悤�ɂȂ�A������̓V��ł����Ă��u��O�K�E�v�Ə̂���Ȃlj����̎p���������悤�ɂȂ�܂����B
|
|
|
|
���c�F�E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |
|
|
|
�]�ˏ�ɂ͌x���v���̋l���Ƃ��đ����̔ԏ�������܂������A���ݎc���Ă���̂�3�����ł��B |
|
|
|
�S�l�ԏ��B
|
���S�ԏ��B
|
|
|
�k�j����(�����͂˂�����)�̐Ί_�B |
|
|
|
���c���������Ƃ���̐Ί_�B
|
�V�_���̐Ί_�B
|
|
|
22. �����q�� (�����s�����q�s) ���̎j�� �����q��́A���c���ɖ{������������k�����̎O��ځE���N�̎O�j�E�k�����Ƃ��z�����������ɂ������R��ł���B1582�N���ɒz�邪�J�n����A1587�N���܂łɂ���܂ł̑�R��(�����q�s)���狒�_���ڂ����Ƃ����B �@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%9F%8E |
||
|
��ށF���q |
|
|
|
|
|
|
|
���؋ȗՁB(�v�Q�n��) |
|
|
|
���؋ȗւ���͔����q�s�X���悭�����܂��B |
|
|
|
�{�ېՁB(�v�Q�n��) |
|
|
|
���{�ȗՁB(�v�Q�n��) |
|
|
|
���q�ȗՁB(�v�Q�n��) |
|
|
|
�g���B(���ْn��) |
|
|
|
�g�����猩�����a�Ղ̐Ί_�B |
|
|
|
�g����n�����Ƃ���̐Ί_�B |
|
|
|
�Ռ��B(���ْn��) |
|
|
|
���a�ՁB(���ْn��) �o�y������Ղ͖��ߖ߂���A�ʒu���킩��悤�ɕ�����������Ă��܂��B �������Ɍ������͌Ռ�����̓����ŁA�����̖���C���[�W���Č��Ă����ؖ�(���Ԃ�����)�ł��B |
|
|
|
|
||
|
��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j |
||
|
123. ��R�� (�����s�����q�s) ���̎j�� |
||
|
|
|
|
|
124. �i���� (�����s�`��) ���̎j�� |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
��C�����N |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||