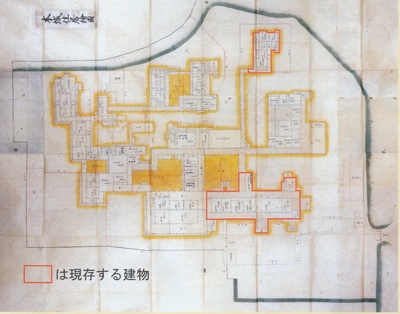11 埼玉県
|
日本100名城 |
||||||
|
続日本100名城 |
118. 忍城 |
119. 杉山城 |
120. 菅谷館 |
|
■Aランク(日本の100名城) |
||
|
18. 鉢形城 (埼玉県寄居町) 国の史跡 鉢形(はちがた)城は武蔵国鉢形にあった、戦国時代の連郭式平山城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%A2%E5%BD%A2%E5%9F%8E# |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
||
|
外曲輪。 |
|
|
|
深沢川。 |
|
|
|
荒川。 |
|
|
|
二の曲輪。 |
|
|
|
二の曲輪と三の曲輪(奥)の間にある堀。 |
|
|
|
二の曲輪(右)と三の曲輪(左)の間の堀と土塁。 |
|
|
|
堀と角馬出(右)。 |
|
|
|
二の曲輪南側の馬出。 |
|
|
|
三の曲輪。 |
|
|
|
虎口。 |
|
|
|
復元四脚門。 |
|
|
|
復元石積土塁。 |
|
|
|
本曲輪。 |
|
|
|
本曲輪から見た荒川。 |
|
|
|
19. 川越城 (埼玉県川越市) 県の史跡 川越城は武蔵国入間郡にあった比高5〜6mの平山城で、1457年に扇谷上杉氏の命により太田道真、太田道灌父子によって築かれた。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%9F%8E |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
||
|
本丸御殿。(県指定有形文化財) |
|
|
|
当時は16棟、1025坪の規模をもっていましたが、明治に入ると廃城令で多くの建物は解体され、現在残る建物は玄関・大広間部分と家老詰所のみとなっています。 〜画像はパンフレットより〜 |
|
|
|
玄関。 |
|
|
|
大広間。 |
|
|
|
御殿廊下。 |
|
|
|
家老詰所。 |
|
|
|
家老詰所内部。 |
|
|
|
富士見櫓跡。 |
|
|
|
中ノ門。 |
|
|
|
中ノ門堀跡。 |
|
|
|
三芳野神社。 |
|
|
|
そのため「行きはよいよい、帰りは怖い……」と歌われる童謡「とおりゃんせ」の舞台と言われています。 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Bランク(続日本の100名城) |
||
|
118. 忍城 (埼玉県行田市) 県の史跡・復興天守 |
||
|
|
|
|
|
119. 杉山城 (埼玉県嵐山町) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
120. 菅谷館 (埼玉県嵐山町) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Cランク |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||