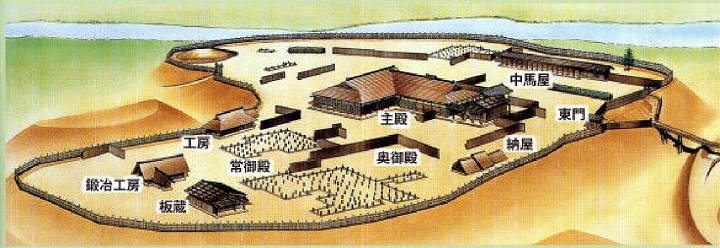02 青森県
|
日本100名城 |
||||
|
続日本100名城 |
103. 浪岡城 |
|
4. 弘前城 (青森県弘前市) 重要文化財・国の史跡・現存天守 弘前城は、陸奥国鼻和(はなわ)郡にあった城で、江戸時代に建造され、弘前藩津軽氏4万7千石の居城として、津軽地方の政治経済の中心地となった。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%9F%8E |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
天守。(国の重要文化財)
|
|
|
|
天守から見た岩木山と咲き始めの桜。
|
二の丸東門。(国の重要文化財)
|
|
|
内堀。
|
外堀。
|
|
|
5. 根城 (青森県八戸市) 国の史跡 根城は、陸奥国糠部郡(ぬかのぶぐん)にあった城で、本丸・中館・東善寺・岡前舘・沢里館の5つの館(曲輪)が連なる連郭式の平山城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%9F%8E |
||
|
取材:文子 |
|
|
|
|
|
|
|
旧八戸城東門。 |
|
|
|
堀跡。(配置図①) |
|
|
|
堀跡。(配置図②) |
|
|
|
中館址。(配置図③) |
|
|
|
本丸。(配置図④) |
|
|
|
木橋。 |
|
|
|
本丸跡の復原図。 復原図は八戸市博物館ホームページより。
|
||
|
東門。 |
|
|
|
中馬屋。 |
|
|
|
納屋。 |
|
|
|
主殿。 |
|
|
|
主殿内部。
|
|
|
|
主殿・広間。 |
|
|
|
常御殿。
|
奥御殿。
|
|
|
工房。 |
|
|
|
鍛冶工房。
|
|
|
|
板蔵。
|
|
|
|
|
||
|
■Bランク(続日本の100名城) |
||
|
103. 浪岡城 (青森県青森市) 国の史跡 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
■Cランク |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||